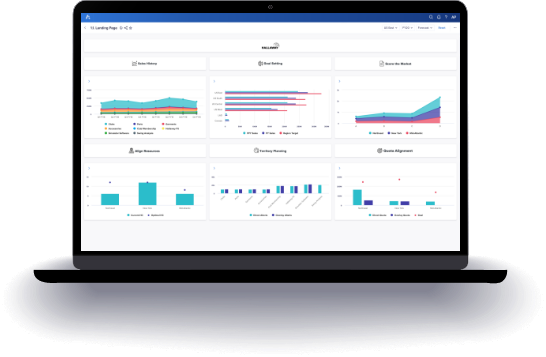S&OPがSCMのデメリットを補ってサプライチェーン管理の高度化を実現


SCM(Supply Chain Management)は、開発、材料の調達、製造、物流、販売を経由して製品が顧客に届くまでの一連の流れを可視化し、管理する手法です。SCMでは必要な量の製品を必要なだけ滞りなく供給することに重きが置かれ、数量ベースでのデータ管理で運用されています。しかし、経営に重要なのは収益であって金額ベースのデータで管理・運用をしていないSCMでは経営計画との乖離が生じる問題があり、それを解決できません。極端な場合、SCMによる運用で数量ベースでは問題がなくても、金額ベースの収益では計画を達成できないという問題が起こり得ます。このようにSCMでは経営計画との乖離を解決できないため、SCMに替わってS&OP(Sales and Operations Planning)という手法が注目されています。そこで、S&OPとは何か、S&OPが必要な背景・理由、SCMに替わってS&OPの手法を導入するメリット、およびS&OPに関連するIBP(Integrated Business Planning)との違いについて解説します。
S&OPとは
S&OPの定義とSCMとの違い
S&OPとは、SCMと同様に製品の開発から販売、消費に至るまでの一連の流れ(サプライチェーン)におけるデータを各業務部門と経営サイドが共有し、迅速な意思決定でサプライチェーン全体を最適化するオペレーション手法のことです。従来のサプライチェーン管理手法であるSCMは、数量を軸としてデータを共有し、在庫の適正化と納期遵守を目的としたオペレーションを行います。一方、S&OPは、数量と金額の両方のデータが共有され、金額を軸として事業計画の達成(利益)および最大化を目的としたオペレーションを行う点で大きく異なります。
SCMからS&OPへ移行が必要な理由
製品を開発して市場に供給するメーカー、あるいは商品を仕入れて販売する卸・小売業者は、サプライチェーンの流れのなかで必要なデータの共有ができないと、製品や商品の過不足、供給の遅れなどが生じます。その結果、売り逃しによるビジネスチャンスの逸失、あるいは過剰在庫の山ができて在庫コストの増大を招き、場合によっては廃棄や処分販売などを余儀なくされ、経営に大きなダメージを与えかねません。また、直接的な経営への影響だけでなく、対外的には顧客や取引先から信頼を失うリスクも考えられます。そこで、企業はSCMで数量をベースとしてサプライチェーンの管理を行うことで在庫の適正化と納期の厳守を目指しました。しかし、SCMとして問題がなくても、事業計画を収益から見ると売上・利益計画が達成できないという問題が多く起こるようになります。そこで、SCMに替わってS&OPによるサプライチェーンの管理が必要とされるようになりました。S&OPは、数量と金額のデータを共有し、経営視点での意思決定を行うことで利益と需要と供給のバランスを調整し、利益の最大化を実現させます。例えば、数量ベースの管理では販売が好調で在庫が底をつくと予測されれば、工場へ増産依頼を単純に行います。しかし、増産することは工場の経費が上昇するため、どの製品をいくら増産するのが事業全体で最も利益が大きくなるかは、金額ベースでの判断が必要です。数量ベースだけの判断では、極端なケースの場合、増産によって利益が減る可能性があります。
S&OPは短期・個別最適ではなく中期・事業全体の最適化が目的
S&OPでは、短期間での個別製品の販売・生産計画の最適化を目的とするのではなく、2年程度の中期間で事業全体の販売・生産計画を原則として月次単位で見直しての最適化を図ります。
S&OPが必要な背景・理由と導入のメリット
SCMに替わってS&OPが必要な理由は、数量ベースのオペレーションでは、経営に直結する事業計画の達成に必ずしも貢献しないことですが、その背景・理由と導入するメリットについて紹介します。
S&OPが必要な背景・理由
現代の経営環境は、グローバル化による競争の激化、デジタル化の進展など技術革新の加速、消費者ニーズや価値観の多様化、製品ライフサイクルの短期化、eコマースの利用拡大や所有価値より使用価値を重視するなど購買行動の変化などが起きています。そして、あらゆる分野においてそれらの変化の幅は大きく、スピードが速く、かつ不安定・不透明・不確実性が増しています。かつては需要予測に対する販売見込みから供給数を合わせるオペレーションの最適化で事業計画は達成できていました。しかし、現在の経営環境では価格や需要の急激な変動に対して事業計画で最も重要な利益を最大化させるためには、金額ベースで財務を最適化できるS&OPによるオペレーションでなければ事業計画の達成が困難になっています。
また、SCMによるオペレーションは、どちらかといえば重要な経営判断が不要な現場サイドが主に行うため、需要に対して供給が不足していると、収益を考慮しないで人件費やその他コストを追加投入する判断がなされる可能性が高くなります。この判断は、SCMのオペレーションの観点から問題がなくても、経営全体から見ると、別のことに経費を投入したほうが、より大きな利益を得られることも考えられるためS&OPによるオペレーションでなければ最適な経営判断はできません。
S&OPを導入するメリット
S&OPの導入で得られるメリットは、まとめると現場サイドによる数量ベースのオペレーションに金額ベースによる経営判断を加えたオペレーションができることで、「在庫適正化と納期遵守だけでなく、事業計画(利益最大化)の目標達成の確度を高められる」ことです。
S&OPを発展させたIBPとは
IBPとは、S&OPを進化・発展・統合させてサプライチェーン全体の管理を行うのみならず、企業が各事業部門において個別に遂行している事業計画の戦略、財務、業務を統合し、予測の精度、効率、予算編成、計画立案の一貫性を目指すソリューションのことです。一般的に企業内では各事業部門がそれぞれ事業計画に取り組んでおり、その情報が各事業部門で共有されていません。そのため、「事業全体のパフォーマンスが見えない」「戦略、ファイナンス、および業務の整合性が取れない」「事業をこえた連携が実現できていない」「予測、計画、予算編成のスピードが遅れ正確性に欠ける」などの問題が起きています。S&OPの進化形であるIBPは、社内事業部門をこえて、社外のさまざまな利害関係者ともつながり、最新情報が共有できることから、これらの問題を解決し、業務効率を最大化し、業績の向上を実現させます。
S&OPでサプライチェーンの強化がこれからの経営環境には必要
これまでの長い間、数量をベースとした管理のSCMでサプライチェーンが堅持されてきました。しかし、現在の経営環境では、SCMでは在庫水準や納期の問題は起きなくても、事業計画の利益を達成できない問題が起きる可能性が高まっています。そこで、SCMに替わって金額ベースで経営視点からサプライチェーンを管理できるS&OPが注目を集めています。これからのサプライチェーン管理にはS&OPを利用することが欠かせないといえるでしょう。